センターだより
中堅教諭等資質向上研修(中学校教諭)
・「校務を推進する企画力(カリキュラム・マネジメントの実践)」
千葉大学教育学部 天笠 茂 特任教授
・「教員としての倫理観の高揚(教員の身分と服務)」 教育振興部教職員課管理主事
・「保護者との信頼関係づくり(人権・いじめ対応を含む)」 教育振興部児童生徒課指導主事



研 修 の 様 子
受講後の、受講生の声です。
・「『目的なくして改革なし』という講師の言葉が心に残った。学校全体のことを踏まえ、自分のできることを考えていきたい。」
・「目指す生徒像実現に向けて、以前のやり方を踏襲するのではなく、カリキュラム・マネジメントに取り組んでいきたい。」
・「生徒の行動の背景をしっかりと考え、信頼関係づくりに努めていきたい。」
中堅教諭としての資質・能力の向上に努め、職場の活性化や若手教員への助言・指導等、積極的に校務推進に参画していただくことを期待しております。
主幹教諭研修
・「業務改善について1」ー校務のICT化を推進する工夫と実際ー 公立小学校校長
・「業務改善について2」ー学校における働き方改革の工夫と実際ー 教育振興部教職員課管理主事
・「業務改善について3」ー他校の実践に学ぶー
県立高等学校教頭、県立盲学校教頭、県立特別支援学校教頭
総合教育センター所員



研 修 の 様 子
受講後の、受講生の声です。
・「ICTの活用が業務改善に大きくつながることが分かった。個人としても学校としても活用したい。」
・「講師の方の、事務仕事は『効率』、子供に関わることは『能率』という話が印象に残った。限られた時間でいかに子供と向き合っていくか、考えていきたい。」
・「班別協議では、他校の様々な実践を学んだ。自校の課題に生かしていきたい。」
主幹教諭として学校運営に参画し、教員の業務改善についてより一層推進していただくことを期待しております。
高等学校におけるALの視点にたった授業づくり研修
9月18日、高等学校におけるALの視点にたった授業づくり研修が行われました。本研修の対象は、本センターが指定した高等学校から推薦された高等学校教員60名です。以下の内容で講義・講話・演習・協議が行われました。
・「授業改善の視点」 県教育振興部学習指導課指導主事
・「高等学校授業ライブラリの活用について」 県総合教育センター所員
・「指導案検討<班別協議><全体協議>」 県総合教育センター所員



研 修 の 様 子
受講後の、受講生の声です。
・「生徒に身に付けさせるべき能力について確認できた。ALの様々な手法を授業に生かしていきたい。」
・「高等学校授業ライブラリの、学習活動の動画やワークシートなど今後活用していきたいと思った。」
・「他校の取組を知ることができて良かった。実践したい内容も多く、実り多い協議となった。」
本研修で学んだことを生かし、指導力の向上、授業改善に結び付けていただくことを期待しております。当センターコンテンツ高等学校授業ライブラリについて、ぜひご活用ください。
プログラミングデーinちば2019
・「プログラミング教育の意義について」 放送大学 中川 一史 教授
・「校内で推進していく手立て」 県総合教育センター所員
・「プログラミング体験研修(Scratch)」 県総合教育センター所員






研 修 の 様 子
受講後の、受講生の声です。
・「校内研修の進め方、授業の進め方を動画で分かりやすく学べた。校内での実践につなげたい。」
・「プログラミング教育の意義がよくわかり、授業に対するイメージをもつことができた。」
・「プログラミング体験は本当に楽しかった。授業を行うのが楽しみになった。」
来年度から、小学校で必修化されるプログラミング教育について、各校の中心として実践を推進していただければ幸いです。 当センターコンテンツ「はじめてのプログラミング授業ガイドビデオ」についてもご活用ください。
小学校外国語科・外国語活動研修
・「1ユニットの単元計画と指導の実際」・「教材を活用した具体的な指導方法」
・「1ユニットの単元計画の作成/マイクロ・ティーチングの準備」
・「模擬授業」 講師:公立小学校教員
・「小学校教諭に期待することー外国語教育の観点からー」 敬愛大学国際学部国際学科 向後 秀明 教授






研 修 の 様 子
受講後の、受講生の声です。
・「講師の方から様々な授業アイディアを学んだ。外国語に積極的にチャレンジしていきたい。」
・「マイクロ・ティーチングでは、授業づくりのヒントや資料の使い方をたくさん学ぶことができた。」
・「苦手意識があったが、『やってみると楽しい』と思った。今後の授業に生かしていきたい。」
外国語によるコミュニケーション能力は、生涯にわたる様々な場面で必要とされることが想定されています。子供たちが外国語に慣れ親しめるよう、教材を効果的に活用し、よりよい実践へとつなげていただくことを期待しております。
ユニバーサルデザインの視点を踏まえた授業づくりや学級づくり研修
・「ユニバーサルデザインの視点を踏まえた学級経営の在り方について」
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 滑川 典宏 主任研究員
・「通常の学級におけるユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりや学級づくりの実際」
・「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりや学級づくりで担当としてできること」
市町村教育委員会指導主事
公立小・中学校教員/県立高等学校教員
県総合教育センター所員






研 修 の 様 子
受講後の、受講生の声です。
・「子供の視点で考え、子供を大事にした授業実践、学級経営をしていきたい。」
・「『なくてはならない支援』と『あると便利な支援』について具体的な実践例を学べてよかった。」
・「どの校種にも共通して大切な視点を学んだ。異校種の先生との情報交換の場は有意義だった。」
本研修で学んだことを生かし、子供たちの「わかる」「できる」授業づくりや学級づくりを推進していただくことを期待しております。
小学校理科すぐに役立つ観察・実験研修
・「理科の基礎実験・実習」 講師:公立小学校教員
〇実験における安全指導 〇ものの温度と体積に関する実験・実習
・「生命・地球区分の観察実験・実習」 講師:公立小学校教員
〇千葉県の地層 〇堆積実験 〇モデル実験に基づいた学習の進め方



研 修 の 様 子
受講後の、受講生の声です。
・「すぐに授業でやってみたいと思った。器具の準備や、予備実験を大切にしていきたい。」
・「安全に実験するための準備や工夫について学んだ。他の分野の研修も受けてみたい。」
・「子供の目線に立って研修に参加できた。子供たちの理科への関心を高めていきたい。」
本研修で学んだことを生かし、子供たちが見通しをもって観察、実験を行い、問題解決の力を養えるよう支援していただくことを期待しております。
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業デザイン研修
以下の内容で講話・演習・協議が行われました。
・「これからの社会を生き抜く児童生徒が身に付けるべき資質・能力とは」 民間企業講師
・「主体的・対話的で深い学びを実現する授業デザインを学ぶ」 民間企業講師
・「これからの社会を生き抜く児童生徒の資質・能力を育成するための指導の先行実践」
・「実践を考え共有しよう」
北海道札幌市立伏見小学校 朝倉 一民 主幹教諭
鳥取県岩見町立岩見中学校 岩崎 有朋 教諭






研 修 の 様 子
受講後の、受講生の声です。
・「プロジェクト型アプローチの考え方と実践例を学ぶことができた。実践につなげたい。」
・「従来の指導法にとらわれず、私たちが主体的に授業デザインをしていくことが大切だと思った。」
・「授業の新しいスタイルや、今後の方向性を学びワクワクした。学校全体を巻き込んでいきたい。」
これからの社会を生き抜く子供たちが身に付けるべき資質・能力を見据え、学習者中心の多様な学びについて、より一層推進していただくことを期待しております。
教育情報化推進リーダー養成研修
以下の内容で講義・情報提供・グループ演習が行われました。
・「研修の目的と県の現状」 県総合教育センター 所員
・「教育情報化推進リーダーの役割」 県総合教育センター 所員
・「これからのICT教育に必要なもの」 日本教育情報化振興会 赤堀 侃司 会長
・「教育の情報化の最新事情」(情報教育の最新事情、情報モラル教育、プログラミング教育)
放送大学 中川 一史 教授
・「勤務校の現状と情報リーダーとしての心構え」 県総合教育センター 所員



研 修 の 様 子
受講後の、受講生の声です。
・「学校CIO補佐官の責務を果たし、情報教育をリードしていきたい。」
・「情報活用能力が学習の基盤となる資質・能力に位置付けられた。今まで以上に力を入れたい。」
・「Society5.0を踏まえ、使うためのICTではなく、子供の思考に合わせて効果的に活用できるようにしたい。」
情報教育や校務の情報化を推進し、教育の情報化に向けた校内の組織づくりの補佐役としてリーダーシップを発揮していただくことを期待しております。
研修履歴システムの本格運用に係る市町村教育委員会研修担当者会議
7月16日、本センターにおいて、研修履歴システム「Asttra」の本格運用に係る第1回市町村教育委員会担当者会議が行われました。各市町村教育委員会研修担当者に、以下のとおり説明いたしました。
・千葉県・千葉市教員等育成指標と教職員研修体系に基づく研修事業について
・研修履歴システム「Asttra」の機能について
・各市町村教育委員会が主催する研修事業の「Asttra」への登録について
・「Asttra」試行運用、本格運用に向けたスケジュールについて

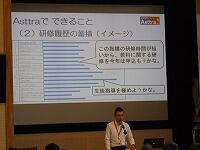
令和2年度から、本格運用される、研修履歴システム「Asttra」が円滑にスタートできるよう、今後ともご協力をお願いいたします。

 アクセス
アクセス サイトマップ
サイトマップ